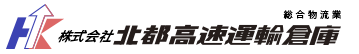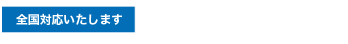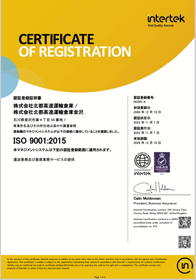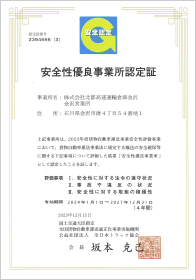品質保証への取組み
主な安全への取組み
運行管理

全車輌へのデジタルタコグラフ、ドライブレコーダーの搭載を完了し、安全運行・適正運行の個別指導を実施しております。
さらに運転者が適正運行の重要性を自覚するよう、輸送安全規則や道路交通法といった法規制の指導もおこなっております。
安全研修

大手物流企業・自動車メーカー・保険会社等から、安全指導担当者を招き、車輌の基礎知識・日常点検講習等の実習研修や安全講話やKYT講習による安全管理知識の習得に努めております。
運転者自らが精度の高い点検方法の習得や運行法規の理解に努 めます。
飲酒管理

印字機能付飲酒検知器を導入し、出発時・帰社時に呼気検査を実施。
飲酒に関する社内規定を設け、飲酒運転の恐怖と社会的責任の重さについて指導を徹底し、プロドライバーとしての自覚を促します。
組織管理
安全会議を機能させ事故の削減に努めます。



| 安全会議の種類と特徴 | ||||
| 会議名 | 出席対象者 | 開催日及び 実施回数 |
内容 | |
| 北都高速協力会会議 | 社長 各グループ会社 社長 |
毎月 第2土曜日 |
事故状況報告 | 改善対策・事故処理状況の確認・事例検証 |
| 実績報告 | 北都高速および各グループ会社実績報告 | |||
| 営業報告 | 荷主別実績報告・顧客情報の報告と対策 | |||
| 適正実務確認 | 点検表による業務内容の確認・コンプライアンス管理 (ISO社内規定・Gマーク基準・法規制に基づく) |
|||
| 業務指示 | 労務管理、安全衛生指示・事故事例に対する改善指導 | |||
| グループ会社対応 | 各グループ会社会議併催 | |||
| 安全衛生委員会 事故処理委員会 |
社長 委員長 安全管理者 衛生管理者 (安全衛生推進者) 部門管理者 運転各班 班長 副班長 班員 |
毎月 第2土曜日 |
安全衛生に 関わる 調査審議事項 (規則第17条・18条) (規則第21条・22条) |
労働者の危険を防止するための基本対策 |
| 労働者の健康障害防止、健康保持増進のための基本対策 | ||||
| 労働災害の原因および対策で安全衛生に関すること | ||||
| その他労働者の危険防止、健康障害防止に関する重要事項 | ||||
| 交通安全対策 | 国交省指導監督指針に基づく教育の実施 (安全計画年間教育表に基づく。) |
|||
| 課題検証 | 班会議へのテーマ選定・要点指導の提案 | |||
| 検討事項、注意事項のとりまとめ。 | ||||
| 意見聴取 | 要望事項検討、決済・質疑応答 | |||
| 事故状況報告 | 事故状況の詳細報告・乗務員の事故状況説明 | |||
| 改善対策 | 事故検証・防止策討議 | |||
| その他 | 緊急指導の実施・顧客情報の周知 | |||
| 班会議 | 部分管理者 班員 全員参加 |
毎月 1回 班毎に決定 |
会議内容の報告 | 班員への安全衛生委員会の内容報告 |
| 課題対応 | テーマ対応(技術指導・事故事例検証) | |||
| 専門指導 | 事故、不具合等の重要性、荷主からの要請に 応じて専門指導を実施。 |
|||
| 意見聴取 | 要望事項検討・質疑応答 | |||
| 安全衛生大会 | 全員 | 年4回 | 交通安全対策 | 国交省指導監督指針に基づく教育の実施 過労・飲酒運転の撲滅への指導 等 |
| 貨物事故対策 | 荷物に応じた正しい積載方法の確認 | |||
| 荷主対応 | マニュアル、注意事項等の再確認 | |||
| 意見聴取 | 要望事項検証・質疑応答 | |||
| その他 | 健康管理指導・外部講師による安全講話 | |||
その他の運転指導
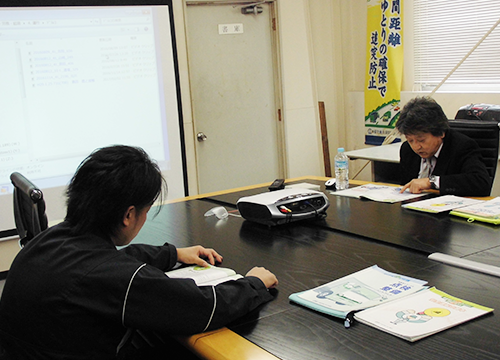


| その他の運転指導 | ||||
| 指導名 | 対象者 | 実施期間 | 指導内容 | |
| 初任運転者指導 (国交省指導監督指針に 基づく初任者教育) |
初任運転者 | 入社から 3ヶ月以内 |
テキスト研修 | プロドライバーとしての心構え、安全運転技術の取得 |
| 添乗指導 | 運転技術、積載技術の取得・ワンマン運転への見極め | |||
| 適正診断 | 外部期間による運転適性検査 | |||
| 点検整備研修 | トラックの構造、点検方法の取得 | |||
| 運転特別指導 | 事故当事者 新人運転者 等 |
随時 (土曜日実施) |
プロドライバーとしての役割、責任への意識改革 事故事例検証・改善対策指導 |
|